導入
中枢性尿崩症の簡単な解説です。こんな疑問を解決できます。
- 中枢性尿崩症ってどんな病気?
- 負荷試験はどこを見れば良い?
- 治療のポイントは?
河野れんといいます。病院薬剤師2年目で色々勉強中です。よろしくお願いします。
バソプレシン(AVP)とは
まずバソプレシンのはたらきについて
- 視床下部の視索上核及び室傍核で産生される
- 軸索輸送により下垂体後葉に運ばれて蓄えられる
- 体循環に分泌され、腎臓の集合管にに存在する AVP V2受容体に作用する
- アクアポリン2を介して水の再吸収を促す
中枢性尿崩症は、このバソプレシンの産生と分泌が障害されている状態です。
腎臓で水を再吸収できないので、薄い尿がたくさん出ることになります。
原因
原因は以下の通りです。
- 特発性(原因不明・13%)
- 続発性(二次的・87%)頭蓋内腫瘍、手術後、炎症など
- 家族性(遺伝)
症状
- 多尿(1日尿量が3000mL以上または40ml/kg以上)
- 高Na血症(150mEq/L以上)
血液が濃くなり、高張性脱水を起こすため、喉が渇いて水をたくさん飲むようになります。
頭蓋咽頭腫の患者さんでは喉が渇かないこともあり、脱水の危険があります。
診断
内分泌学的検査を行い、中枢性尿崩症か、腎性尿崩症か、心因性多飲症かを鑑別していきます。
高張食塩水負荷試験
5%食塩水を0.05mL/kg/minの速度で2時間点滴静注し、Na濃度・AVP濃度を30分ごとに測定します。
この試験により血清Na濃度が10mEq/L上昇するため、検査開始時にNa濃度が150mEq/L以上の場合は避けた方が良いそうです。
- 正常や心因性多飲症:血清Na濃度が上がるため、それを薄めるために水を保持しようとして血漿バソプレシン濃度も上がる
- 中枢性尿崩症:血清Na濃度が上がっても血漿バソプレシン濃度は反応しない
水制限試験
水分制限を6時間半、あるいは体重が3%減少するまで継続し、その間の体重と尿量を30分ごとに測定します。
- 正常や心因性多飲症:バソプレシンが働くため濃い尿が少しだけ出る。
- 中枢性尿崩症、腎性尿崩症:バソプレシンが働かないため脱水などおかまいなしに薄い尿が多量に出る
バソプレシン負荷試験
水制限試験終了後に引き続いて行います。
ピトレシン注射液5単位を皮下注射し、30分後と60分後に尿量と尿浸透圧を測定します。
- 中枢性尿崩症、心因性多飲症:バソプレシンに反応して尿浸透圧が300mOsm/kgH2O以上に上昇する
- 腎性尿崩症:腎臓がバソプレシンを受け取れないため尿浸透圧は低いまま
治療
デスモプレシン投与
デスモプレシン口腔内崩壊錠では1回60mg、経鼻製剤では2.5μgから治療を開始します。
その後、尿量や体重、血清Na濃度を確認しながら用量を調整していきます。
目標となる尿量は1mg/kg/hr、1500~2000mL/日です。
口腔内崩壊錠は食事の影響を受けるため、食前30分あるいは食後2時間以内の投与は避けるようにします。
水中毒に注意
水中毒による低Na血症の予防のため、少なくとも1日1回はデスモプレシンの抗利尿効果が切れる時間帯を確保する必要があります。
尿がたくさん出てから次の薬を飲むように指導しましょう。
水分補給は、喉の渇きに合わせて行います。
バソプレシンを飲み始めると尿量が減りますが、治療前と同じペースで水を飲んでいると水中毒になってしまいます。
自宅で体重を毎日測り、2kg増えたら水を飲みすぎている、2kg減ったら脱水を起こしかけているという目安で調節してもらいましょう。
頭蓋咽頭腫などで喉の渇きのない患者さんは脱水を起こさないよう、尿量に応じた適正な量(1日2L程度)を意識的に飲むようにする必要があります。
以上になります。最後まで読んでいただきありがとうございました。

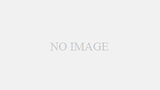
コメント